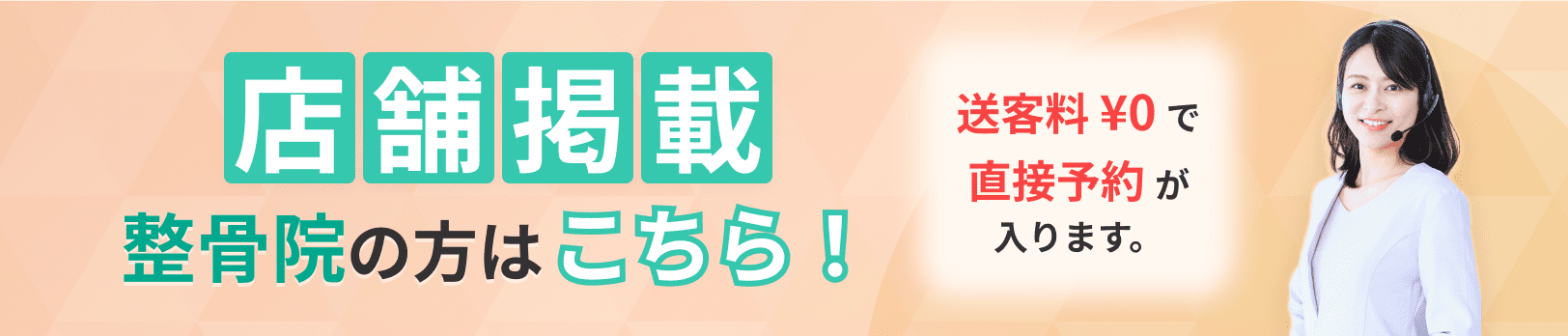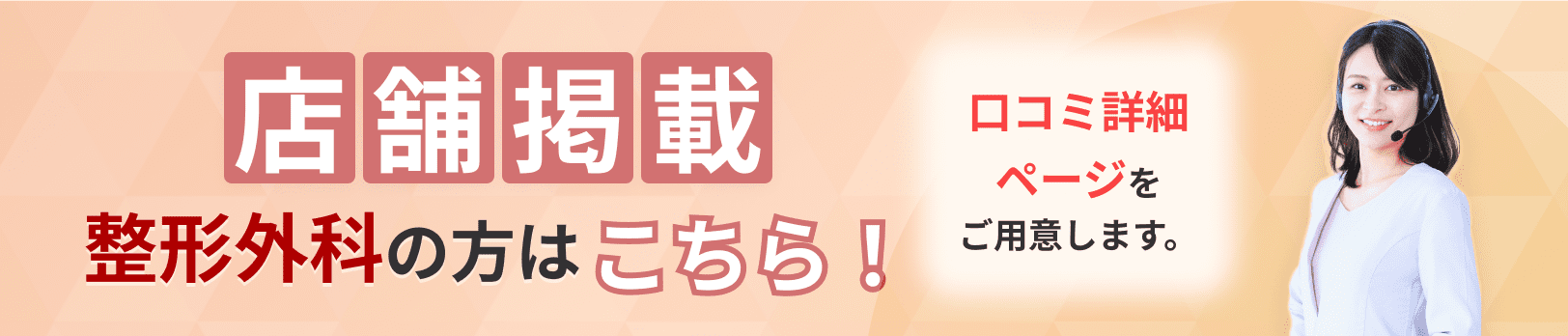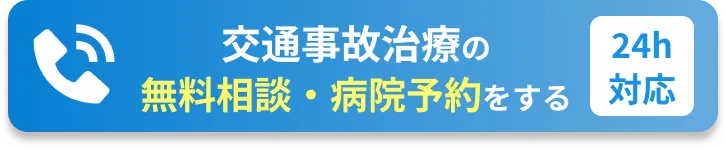交通事故での打撲は通院すべき?慰謝料や後遺症についても解説!

交通事故で打撲は慰謝料をもらえるの?仕事を休んでも良い?と困っている方に向けて、慰謝料の種類や補償、後遺症が残る可能性などについて詳しく解説します。
また、打撲の治療期間や通院頻度に関しても解説しているので、参考にしてください。
交通事故の打撲でもらえる慰謝料の種類と金額の目安

交通事故による打撲で、慰謝料を受け取ることができます。もらえる慰謝料は以下の3種類。
それぞれ詳しく解説していきます。
自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、交通事故で打撲をしたときに、自賠責保険からいくらもらえるかを決めるためのルールのことです。「任意保険基準」「裁判所基準」と比べて最も低い計算基準であり、計算の例を挙げると以下のようになります。
- 4,300円×治療期間の日数
- 4,300円×実通院日数を2倍したもの
自賠責保険基準では、上記2つの計算結果のうち、少ない方の金額が支払われます。また、障害に関する支払い限度額は、120万円です。
ただし、入通院慰謝料での自賠責の上限は、治療費だけでなく「休業損害」や「治療関係費」と合わせて120万円なので注意しましょう。
自賠責保険基準のメリットは、加害者が任意保険に加入していない場合でも最低限の補償が受けられる点です。
任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めた保険基準です。そのため支払基準は保険会社によって異なりますが、慰謝料が多くなるほど保険会社の利益が減ってしまうので、裁判所基準と比べると低額です。理由としては、被害者に支払う慰謝料が多くなるほど保険会社の利益が減ってしまうからです。
また、任意保険は自賠責保険(限度120万円)の不足分を補うのが特徴。多くの任意保険が対人・対物賠償の限度額を無制限としています。さらに、保険会社が損害の算定や示談交渉を行うため、簡単かつ迅速に賠償金の支払いを受けることが可能です。
掲載方法は保険会社によって異なるので、提示金額が低い可能性も十分考えられます。提示金額に疑問を持ったら、示談交渉で増額を求めることを忘れないでください。
保険って難しくてよく分からない…結局自分は慰謝料もらえるのかな?とまだ不安を感じているなら事故治療ナビにご相談ください。24時間無料で電話・LINEで相談を受付中。
専門員が保険や慰謝料など交通事故治療のあらゆるお悩みに一つ一つお答え致します。
裁判所基準

裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれ、交通事故裁判の過去の裁判例を参考にして設定される基準です。弁護士は、裁判基準の賠償額を元に相手と交渉を行います。
裁判所基準は、自賠責保険基準、任意保険基準に比べ計算基準が高く、弁護士が交渉を進めるため、自分で手続きなどを行う必要がありません。
そのため、交通事故後の負担を少なくできるのがメリットの1つです。
交通事故による打撲で慰謝料はいくらもらえる?

交通事故による打撲の慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?
- 全治1週間の場合
- 全治2週間の場合
- 全治1ヶ月の場合
- 全治3ヶ月~の場合
上記の3つのパターンを紹介します。
ご自身の状態に照らし合わせて参考してみてください。
全治1週間の打撲の場合
| 計算式 | 慰謝料 | |
| 自賠責保険基準 | ①4,200円×7日(通院期間) ②4,200円×3日(5日通院した場合)×2 |
①30,100円 ②25,800円 金額の少ない25,800円が支払われる |
| 任意保険基準 | 保険会社によって異なる | – |
| 裁判所基準 | 弁護士によって異なる | 2万円〜5万円(目安) |
全治2週間の打撲の場合
| 計算式 | 慰謝料 | |
| 自賠責保険基準 | ①4,300円×14日(通院期間) ②4,300円×5日(5日通院した場合)×2 |
①60,200円 ②43,000円 金額の少ない43,000円が支払われる |
| 任意保険基準 | 保険会社によって異なる | – |
| 裁判所基準 | 弁護士によって異なる | 4万円〜10万円(目安) |
全治1ヶ月の打撲の場合
| 計算式 | 慰謝料 | |
| 自賠責保険基準 | ①4,300円×30日(通院期間) ②4,300円×10日(10日通院した場合)×2 |
①129,000円 ②86,000円 金額の少ない86,000円が支払われる |
| 任意保険基準 | 保険会社によって異なる | 126,000円(目安) |
| 裁判所基準 | 弁護士によって異なる | 19万円(目安) |
全治3ヶ月以上の打撲の場合
| 計算式 | 慰謝料 | |
| 自賠責保険基準 | ①4,300円×90日(通院期間) ②4,300円×20日(20日通院した場合)×2 |
①387,000円 ②172,000円 金額の少ない172,000円が支払われる |
| 任意保険基準 | 保険会社によって異なる | 378,000円(目安) |
| 裁判所基準 | 弁護士によって異なる | 53万円~(目安) |
交通事故の打撲で慰謝料を受け取る流れ
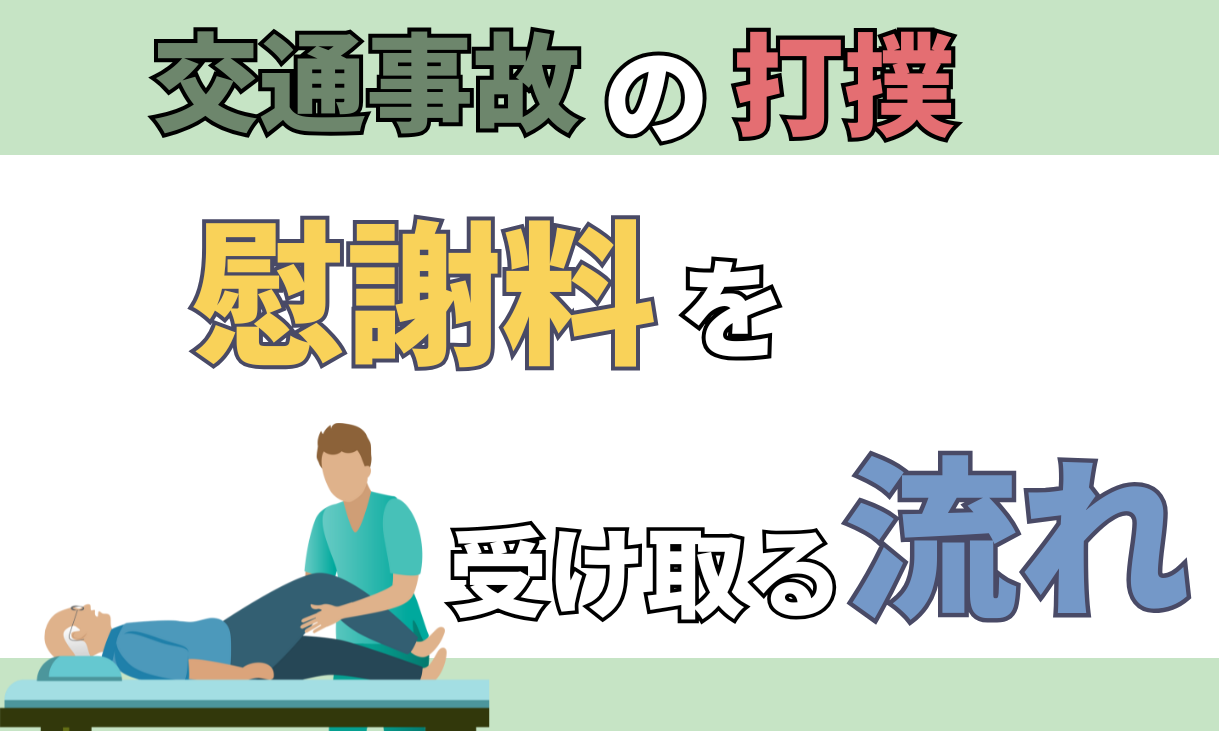
交通事故で打撲を負った場合でも、適切な手続きを踏むことで慰謝料を受け取れます。
下記のような方法で手続きをすることで、スムーズに補償を受け取りましょう。
病院で診断書をもらい人身事故として届け出る
交通事故後に痛みや腫れがある場合は、すぐに病院で診察を受けましょう。
その際、『打撲』と診断されたら医師に診断書を発行してもらい、警察署へ『人身事故』として届出を出してください。
もし、事故が『物損事故』のままだと慰謝料が請求できない場合があるため、人身事故への切り替えはとても重要です。
通院を継続して治療記録を残す
交通事故の慰謝料の算定には、通院日数や頻度が大きく関係します。
少しでも、痛みや違和感が続く間は、通院を継続して治療記録を残すことが大切です。
通院の頻度が少ないと『軽傷』と判断され、慰謝料の減額をされる可能性があります。
痛みがあり通院を続けることは大変かもしれませんが、症状を継続的に診てもらうことで少しでも早く日常を取り戻しましょう。
治療終了後に慰謝料の提示と示談交渉する
医師から『治療終了』の診断を受けた後は、加害者側の保険会社から慰謝料などの賠償額が提示されます。
慰謝料などの賠償額について話し合う際は、治療費だけでなく休業損害なども含めた賠償額の金額を話し合います。
もし、提示額に納得ができない場合は示談交渉を行い、必要に応じて弁護士に相談することも検討してください。
また、一度示談が成立すると原則再請求をすることができないので、慎重な判断が求められます。
交通事故による打撲とむちうちの違いは?
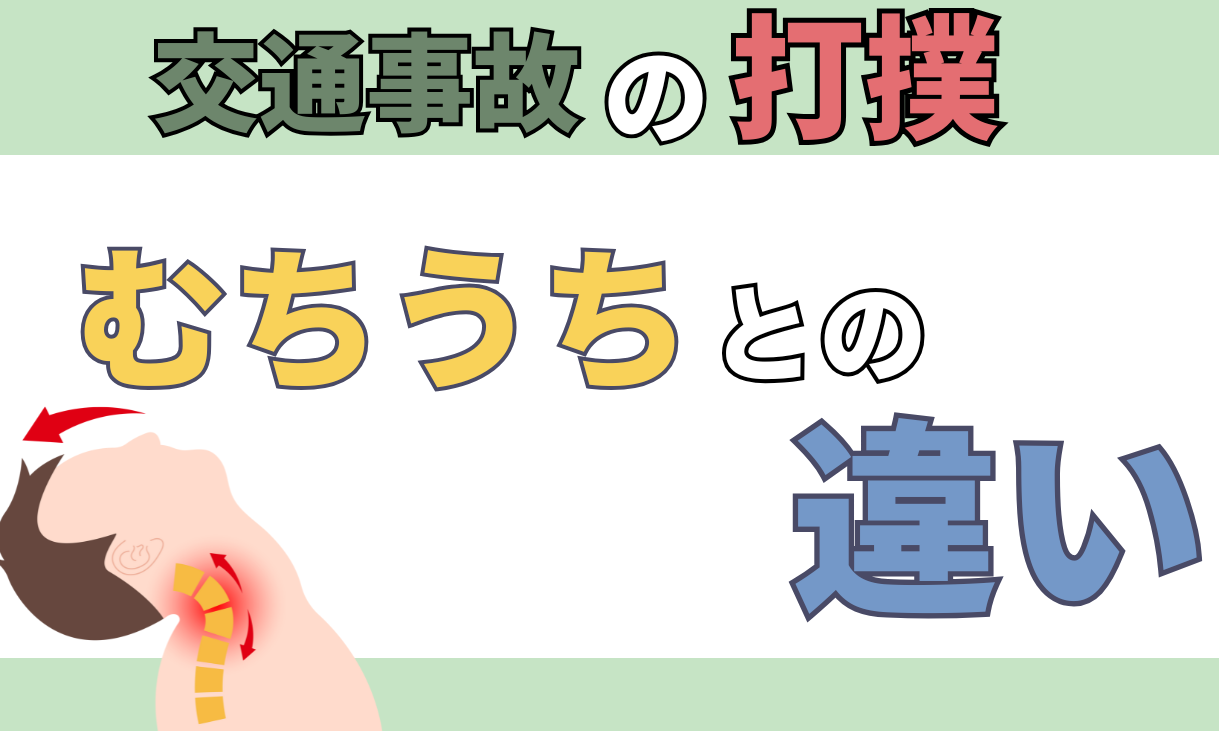
交通事故による打撲とむちうちの違いは、症状はもちろん、治療内容も異なります。
適切な対応をするためには、それぞれの特徴を理解することが大切です。
打撲とむちうちの症状の違い
打撲とむちうちは、どちらも交通事故で見られる怪我の症状です。
打撲は外傷からの衝撃によって、皮膚や筋肉が損傷して腫れや内出血・痛みが生じるのが特徴です。
一方、むちうちは首への強い衝撃によって、頸椎や周囲の神経が損傷されるもので、頭痛やしびれ・吐き気など神経症状を伴うことが多いです。
むちうちの方が打撲よりも見た目で分かりづらく、長引きやすいのも特徴です。
打撲とむちうちの治療内容の違い
交通事故による打撲とむちうちの違いは以下の通りです。
| 打撲 | むちうち | |
| 意味 | 筋繊維や血管が損傷すること | 首に負荷がかかり首周辺を損傷すること |
| 症状 | 【手足】 ・腫れ ・痛み ・皮下出血など 【頭】 ・頭痛 ・吐き気 ・めまい ・ふらつき ・意識障害 ・脳震盪など 【首や背中】 ・痛み ・手足のしびれ ・息苦しさ ・吐き気など 【胸】 ・痛み ・息苦しさ ・吐き気など |
・首周辺の痛み ・知覚障害や筋力低下などの神経症状 ・頭痛やめまい ・耳鳴り ・吐き気など |
打撲はさまざまな部位で発生し、痛みや腫れ、部位によっては息苦しさや吐き気などを催します。特に頭を打撲した場合は意識障害や脳震盪を起こす可能性が高いため、すぐに病院を受診しましょう。
また、むちうちは首周辺に症状が現れることが特徴です。首だけでなく背中や肩、胸などに痛みを感じることもあります。
打撲とむちうちの治療期間の違い
交通事故による打撲とむちうちの治療期間には、下記のような違いがあります。
| 打撲 | むちうち | |
| 一般的な治療期間 | 約1〜3週間 | 約1ヶ月〜3ヶ月 長引くと6ヶ月以上続くこともある |
打撲はむちうちに比べて、比較的短期間で回復することが多いです。
正確な治療期間には個人差がありますが、早めに医師の判断を受けて適切な治療を受けることで、早期回復の鍵となります。
打撲やむちうちの治療に対応している整骨院をお探しの方は『事故治療ナビ』でにご相談ください。弁護士サポートや自賠責保険対応、女性スタッフの有無など、こだわりの条件に合った整骨院を24時間無料でご案内いたします。今なら最大20,000円のお見舞金を贈呈中です。
「どこで治療をしたら良いか悩んでいる」「治療場所の選び方がわからない」など、治療場所でお悩みの方は、お気軽に事故治療ナビへお相談ください。
交通事故による打撲で後遺障害慰謝料を請求する方法

打撲は軽症と思われがちですが、痛みや違和感が長引くこともあるので、注意が必要です。
その場合は、後遺障害として認定され慰謝料を請求できる可能性があるので、適切な手順を知っておきましょう。
病院に通院する
交通事故にあったら、すぐに病院で診療を受けましょう。
医師による診断で『打撲』とされた場合は、定期的に通院し治療を行う必要があります。
通院をすることで、病院に通院記録や医師の所見が後の後遺障害認定の判断材料となるため、重要な情報となります。
事故判断で通院を中断せず、痛みが続く限りは医師の指示に従い通院を続けることが必要です。
症状固定の診断を受ける
一定期間治療を受けても改善が見込めない場合、医師から『症状固定』と判断されます。
症状固定は、後遺障害認定の出発点となり、この診断を受けるためには継続的な通院と医師との十分なコミュニケーションが必要です。
医師に症状を伝える際は、正確に現状を説明することが重要なポイントとなります。
後遺障害等級の申請をして慰謝料を請求する
医師から『症状固定』と診断された後は、後遺障害診断書を書いてもらい自賠責保険へ等級認定の申請を行います。
必要な書類の準備・症状や痛みの内容を、丁寧に記載することが大切です。
不備があると、等級が認知されないこともあるので、申請前に専門家に相談する方法もあります。
等級が認定されれば、それに応じた慰謝料が支払われます。
交通事故での打撲に関するよくある質問

交通事故治療による打撲に関するよくある質問をまとめました。
仕事を休んだ場合の補償はありますか?
交通事故で怪我をして仕事を休んだ場合、『休業損害』として補償を受けることができます。
これは、事故が原因で働けずに得られなかった収入を補うためのものです。
計算方法は、休日日数や収入に応じて金額が算定されます。
会社員の場合は給与明細・勤務証明、自営業の場合は確定申告などが必要になります。
保険会社が薦める医療機関じゃないとダメですか?
いいえ、受診する医療機関は自分自身で選ぶことができます。
自宅や仕事場から通いやすいかどうかや、信頼できるかどうかなどで病院を選びましょう。
軽い打撲でも治療を受けられますか?
軽い打撲でも治療可能です。
どんなに症状が軽くても交通事故による打撲だと診断されれば、自己負担なしで治療を受けられます。交通事故直後は痛みを感じなくても、日が経つにつれて痛みが出てくることもあるため、軽い打撲でも病院を受診しましょう。
どのくらいの頻度で通院するべきでしょうか?
通院の頻度や回数、期間は怪我の程度によって異なります。医師の指示に従うようにしましょう。
ただし、通院の回数が少ない場合は、大した怪我ではないと保険会社に判断され、慰謝料が減る場合があります。仕事や家事が忙しくても、医師の指示通り通院するようにしましょう。
症状固定と診断されたら、もう治療はできませんか?
症状固定後も治療は可能です。
ただし、症状固定後の治療は自費になります。症状固定とはこれ以上治療を続けても症状が改善されない状態です。この先の治療は不必要と判断されるため、症状固定後の治療は交通事故と無関係になります。その結果、症状固定後も治療ができますが、自費となるのです。
示談成立後に、再度請求することは可能ですか?
場合によっては可能です。
示談が成立したときには、予想できなかった後遺障害や症状が著しく悪化した場合など、締結するべきではないのにも関わらず示談が成立してしまったと認められれば、損害賠償を請求できます。





 事故治療ナビについて
事故治療ナビについて お客様相談窓口
お客様相談窓口 お見舞金について
お見舞金について 会社概要
会社概要