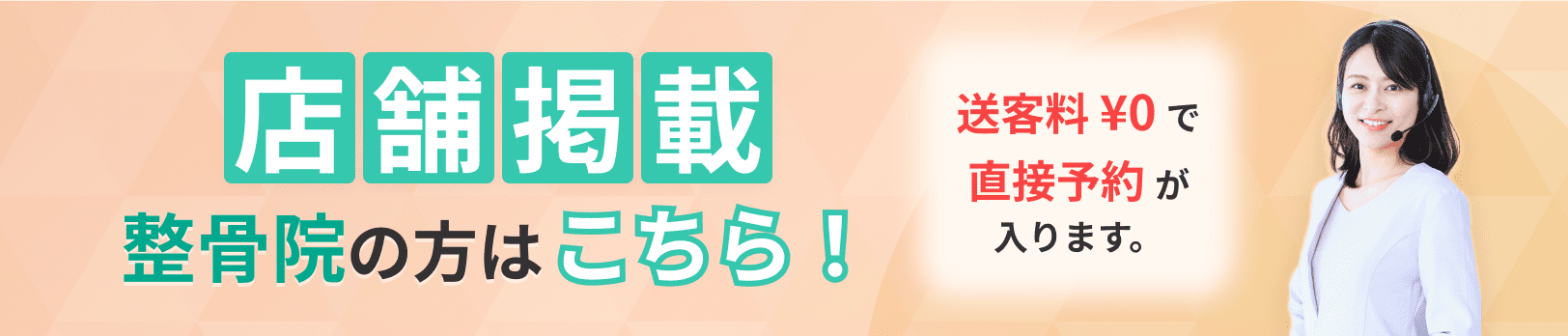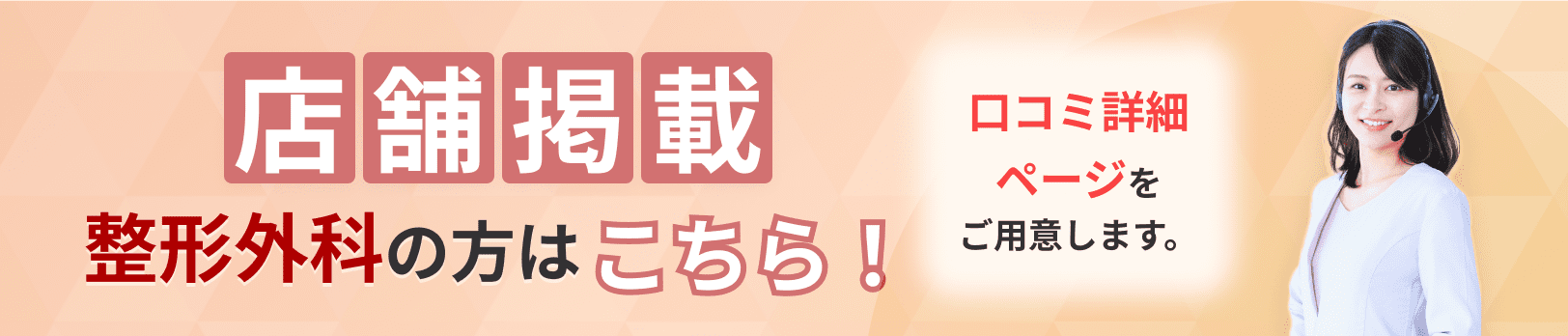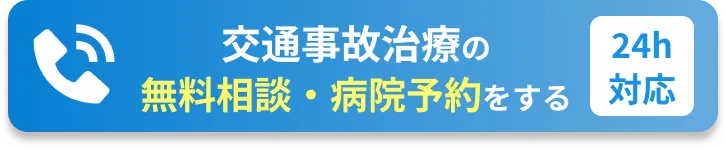交通事故で後遺症が残ったら?後遺障害認定とは?手続きや治療法について解説
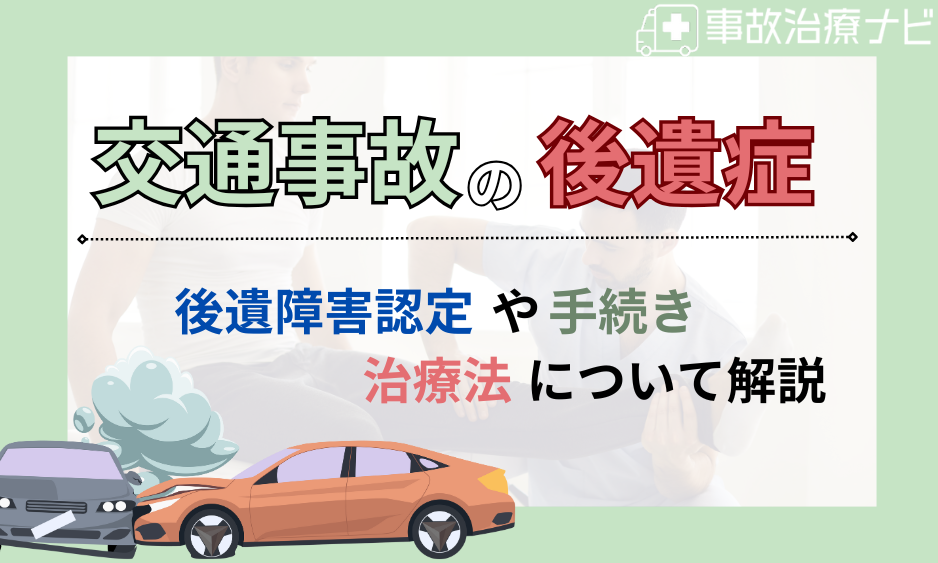
もし交通事故で大きなけがをしてしまい後遺症が残ってしまったらどうすればいいのでしょうか?
後遺症と後遺障害の違い、認定の仕組みや手続きは分かりづらいですよね。
自分の症状は認定されるのか、または治療法に不安を感じる人は多いでしょう。
そこで本記事では後遺障害とは何か?どうすれば認定されるのか?等級による慰謝料の違いや手続きの流
れや仕組み、後遺障害認定審査のポイント弁護士に相談するべきかどうかまで基本から詳しく解説していきます。
後遺障害とは交通事故による後遺症のこと

後遺症と後遺障害の違い
「後遺症」と「後遺障害」は似ている言葉のため、区別されず使われることもありますが、事故による保険の支払い手続きを行うにあたっては、意味が異なります。
「後遺症」とは、治療が終わったものの症状が完治しない状態を指す言葉です。
つまり、交通事故での怪我に関わらず「治療が終了したものの、症状が残っている場合に使われるのが「後遺症」です。
一方「後遺障害」は交通事故に起因する症状であり、機能障害や神経症状などの症状が残っているものを指します。
つまり、「後遺障害」は「後遺症」の一部ということです。
後遺障害の種類
一般的に交通事故の後遺症には以下のようなものがあります。
- 首の痛み(頚椎症・むち打ち・頸椎ヘルニア)
- 腰痛
- 関節の痛み
- 膝の痛み
- 頭痛
- 手足のしびれ
- てんかん
- めまい
- 耳鳴り
- 強い倦怠感
- 睡眠障害
- 非器質性精神障害(うつ病、PTSD等)
交通事故による後遺症とは、治療を終えたものの症状が残り、「症状固定」と診断された症状を指します。
後遺障害とPTSDやうつ病の関係
交通事故では身体的にも精神的にも大きく影響を受けるので身体の治療を行うとともに精神的な治療を行う事が大切です。
身体の自由が奪われ大きなストレスを感じると共に、事故当時の衝撃的な出来事を何度も思い返したり悪夢を見たりすることでPTSDを発症してしまうことがあります。
PTSDの症状が長引くことで心が疲弊し、他の精神障害を併発することが挙げられます。代表的な症状としてはうつ病です。
PTSDとうつ病の併発率は50%とも言われ非常に高い確率です。他にも
- パニック障害
- 摂食障害
- 不安障害
- 素行症
- 人格障害
- 双極性障害
などが挙げられます。PTSDとうつ病は併発しやすいので早めに治療を行いましょう。
後遺障害認定を受けるメリット3選
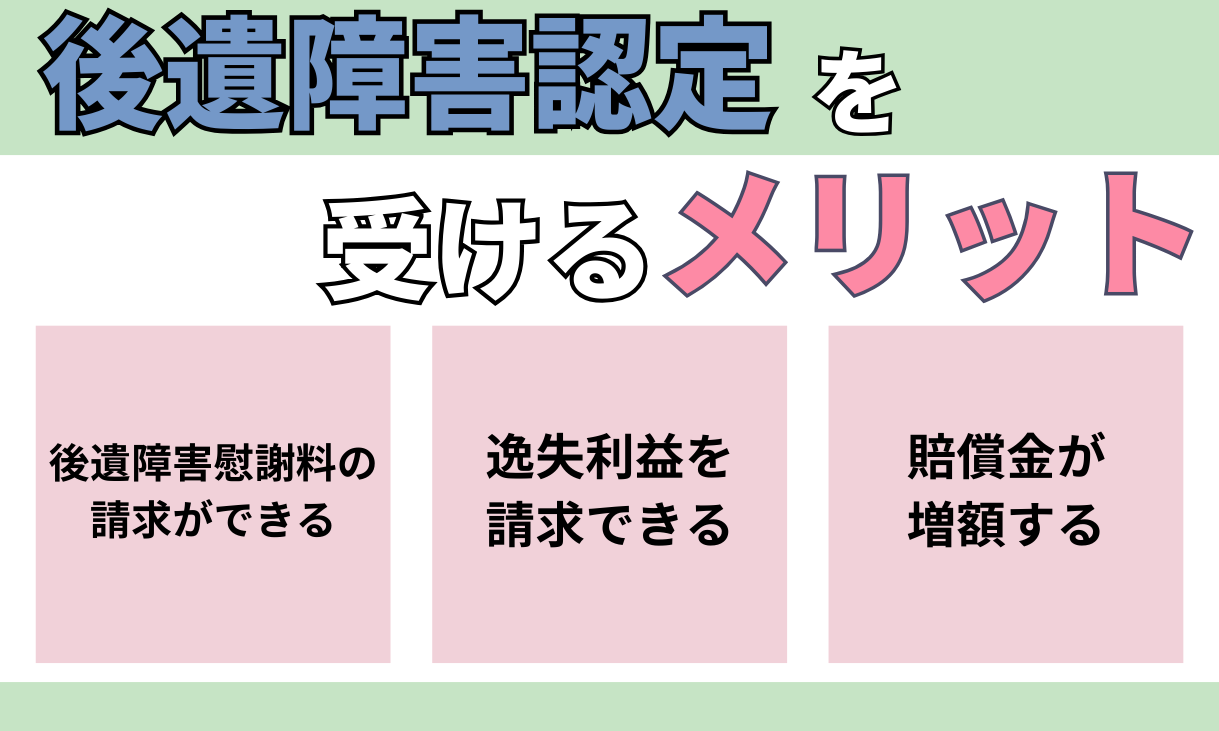
交通事故の後遺障害認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関が行います。
後遺障害認定を受ける主なメリットは以下の3つです。
- 後遺障害慰謝料の請求ができる
- 逸失利益を請求できる
- 賠償金が増額する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
後遺障害慰謝料の請求ができる
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
後遺症が残っていたとしても後遺障害として認定を受けていなければ、後遺障害慰謝料の請求ができません。
後遺障害認定には1級から14級までの等級が存在し、その等級に応じて損害を加害者側へ請求できるようになります。
目安を表にまとめましたので、慰謝料計算の参考にしてみてください。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準(最低限) | 裁判基準( 弁護士あり) |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |
| 第2級 | 998万円(958万円) | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円(829万円) | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円(712万円) | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
引用:アディーレ法律事務所
逸失利益を請求できる
逸失利益とは将来得られるはずだった収入を指します。後遺障害認定を受けることで、交通事故の後遺障害により働けなくなったり働く能力が低下したりした結果、減ってしまった収入を逸失利益として請求できるのです。
また逸失利益には、後遺障害逸失利益だけでなく「死亡逸失利益」も存在します。
死亡逸失利益とは、被害者が死亡したことで被害者が将来に渡って得られるはずだった利益を請求できるものです。
逸失利益の計算方法はそれぞれ異なり、事故前に得ていた収入や年齢などが関係してくるため、不安な場合は弁護士に相談するといいでしょう。
賠償金が増額する
後遺障害認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の2種類の請求ができるようになり、賠償金が増額します。
ただし、等級や自賠責保険基準、裁判所基準によっても基準額が異なるため注意が必要です。
交通事故の後遺障害認定審査の手続きの流れや仕組み

ここからは交通事故の後遺障害認定を受けるために行う、審査手続きの流れや仕組みを解説していきます。
審査手続きはどのような流れなのか、必要な書類などしっかりと理解しておきましょう。
後遺障害認定審査の流れ
後遺障害認定審査の流れは以下の通りです。
- 医師に「症状固定」の診断をもらう
- 医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼する
- 必要な書類を用意する
- 加害者が加入する保険会社に書類を提出する
- 保険会社から審査機関(損害保険料率算出機構)に書類が送られ、審査が行われる
- 加害者側の保険会社を通じて結果が知らされる
書類を提出する加害者が加入する保険会社は、「任意保険会社」と「自賠責保険会社」のどちらかを選ぶことができます。
ただし任意保険会社と自賠責保険会社のどちらを選択するかで、手続きや必要な書類が変化するため注意しましょう。
後遺障害認定審査に必要な書類
後遺障害認定審査に必要な書類は以下の通りです。
【事前認定に必要な書類】
- 後遺障害診断書
【被害者請求に必要な書類】
- 支払請求書
- 請求者本人の印鑑証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書、確定申告書(控)、所得証明書(※事故の影響で休業した日がある場合)
- 通院交通費明細書
- 住民票または戸籍抄本(※被害者が未成年の場合)
- 委任状および委任者の印鑑証明書(※第三者が申請を行う場合)
- その他症状を示す検査結果、追加書類など
- その他損害を立証する書類、領収書など
認定手続きは2種類!事前認定と被害者請求
認定手続きは「事前認定」と「被害者請求」の2種類が存在します。
| 事前認定 | 加害者の任意保険会社に書類を提出する方法 |
| 被害者請求 | 加害者の自賠責保険会社に書類を提出する方法 |
どちらも加害者の保険会社に書類を提出しますが、事前認定と被害者請求にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。
| メリット | デメリット | |
| 事前認定 | 書類を準備する手間がない | 適切な後遺障害等級に認定されないことがある 後遺障害慰謝料の一部を早く受け取ることができない |
| 被害者請求 | 適切な後遺障害等級に認定されやすい 後遺障害慰謝料の一部を先払いで受けられる |
書類を準備する手間がかかる |
事前認定では、書類を準備する手間がかからないものの、申請書類に工夫ができないため、適切な等級の認定を受けられない可能性があります。
一方、被害者請求では書類を準備する手間がかかるものの、申請書類に工夫ができるため、適切な等級の認定を受けられやすいです。
ただし、書類を準備する手間は弁護士に相談することで、解決することができます。
却下されたら異議申立・再審査も受けられる
後遺障害は申請すれば受けられるというものではなく、却下されたり想定よりも低い等級に認定されたりすることがあります。
その場合、損害保険料算出機構に異議申立が可能です。
異議申立は、加害者側の保険会社を通し、損害保険料算出機構に異議申立書などの書類を提出する必要があります。
後遺障害申請には回数制限がないため、損害賠償請求の請求期限内であれば、何度でも異議申立が可能です。
異議申立自体は無料で行えますが、新たに必要となった書類に対して発行手数料がかかるので注意しましょう。
また異議申立には「損害賠償請求権の消滅時効」に注意しなければなりません。
| 傷害分の時効 | 事故翌日から5年 |
| 後遺障害分の時効 | 症状固定翌日から5年 |
時効が成立してしまえば、正しい等級が認められても損害賠償の請求ができなくなってしまいます。
時効の成立が迫っている場合は、異議申立をするべきか、時効の成立を延長させるべきなのか考える必要があるので、弁護士に相談するのがおすすめです。
事故治療ナビなら弁護士サポート付きの整骨院を無料でご紹介します。自宅や職場から通いやすい整骨院を探している方はこちらからお問い合わせください。
今ならお見舞金最大20,000円贈呈しています。
交通事故の後遺症が認定される確率
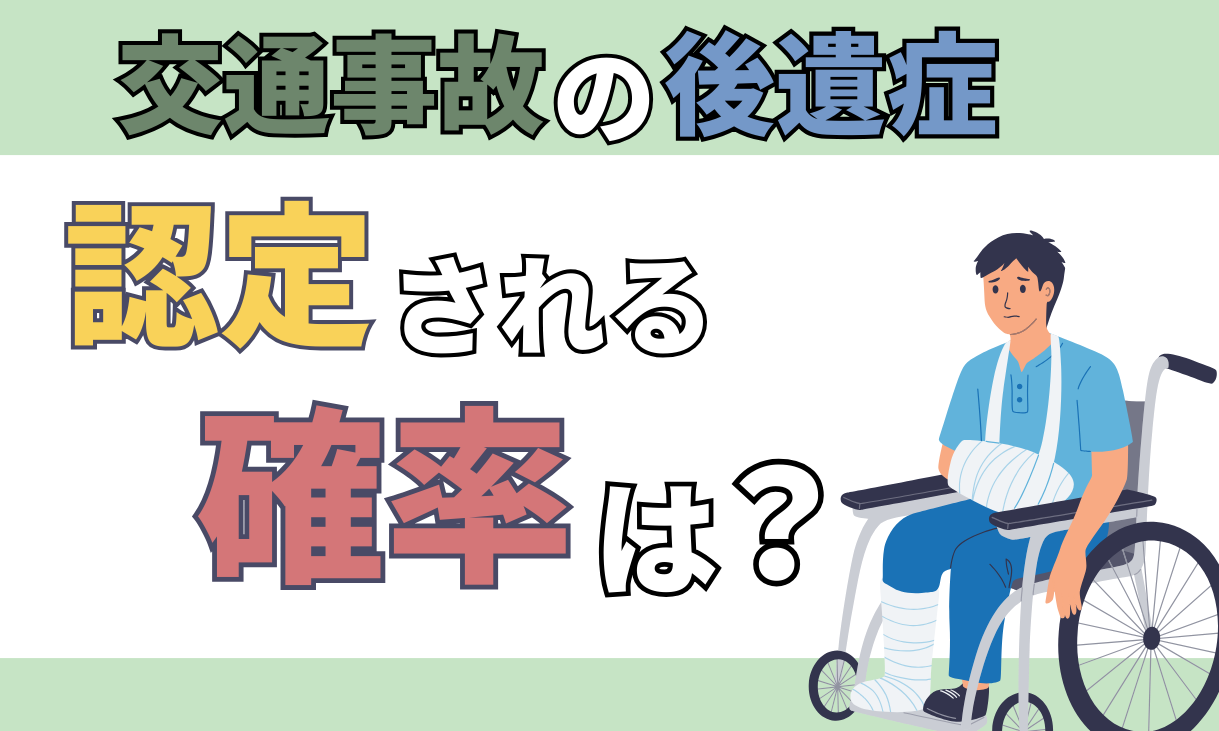
後遺障害認定確率は約5%前後です。
損害保険料率算出機構の統計によると毎年6万件の後遺障害が等級認定されています。
件数だけ見ると多いように感じる人もいるかもしれません。
しかし、損害保険料率算出機構の年間請求受付件数は約130万件と非常に多く、6万件認定されていても、確率は約5%前後と100人中5人ほどしか認定されないのが現状です。
また、後遺障害認定で一番多いのは軽度な第14級であり、全体の約6割。
むちうちで認定されるのは14級である場合がほとんどであり、状況によっては後遺障害に該当しないとされることも多いです。
理由としては、むちうちは画像や医師による他覚的所見が得られない場合が多いからと言われています。
後遺障害の申請を自覚症状に基づいて行わなければならないため、客観的な情報が不足し、後遺障害として認められないケースが多いのです。
また症状が上手く医師に伝わらず、適切な後遺障害診断書を書いてもらえないことや書類が認められないこともあります。
|
等級 |
認定確率の目安 |
|
1~3級 |
5%前後 |
|
4~7級 |
5%前後 |
|
8~10級 |
5%前後 |
|
11~12級 |
5%前後 |
|
13~14級 |
1~2%未満 |
|
非公認 |
70%以上 |
参考 損害保険料率算出機構
後遺障害認定の審査期間
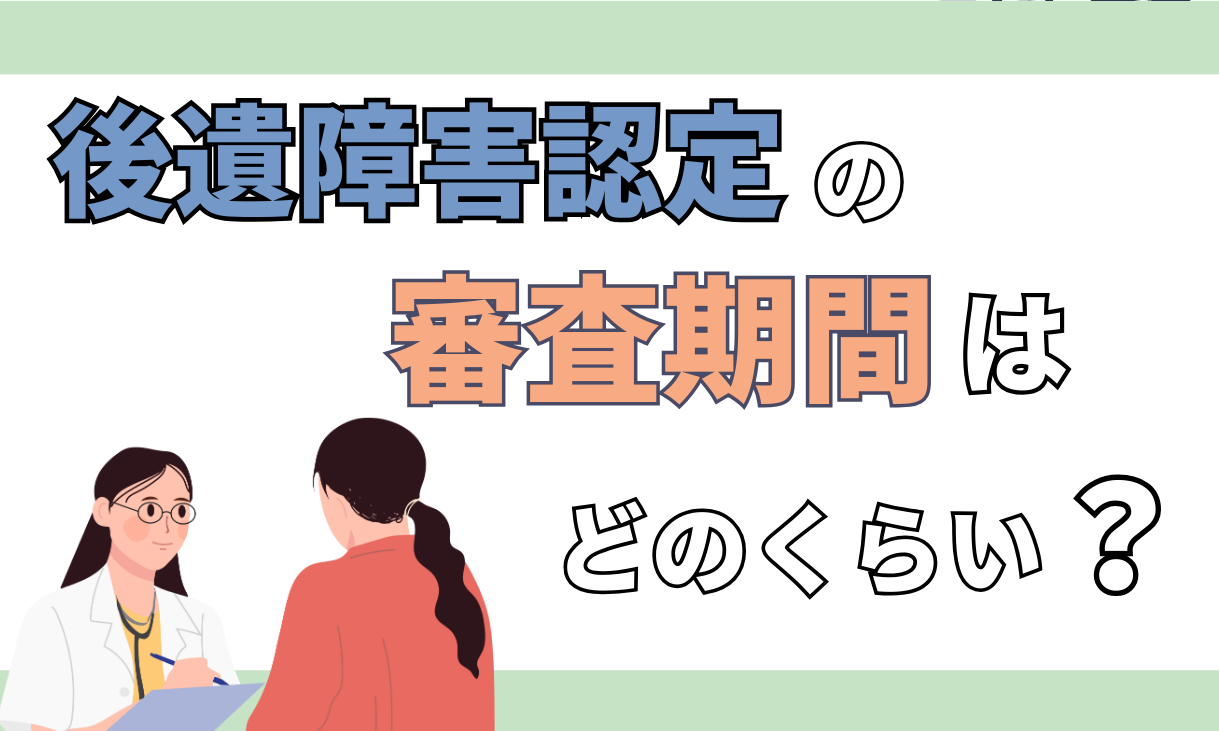
後遺障害認定の審査期間は、早くて30日以内です。
遅くても60日程度で審査が終わりますが、中には1年以上かかるケースも存在します。
後遺障害認定が遅れる理由には以下のものが挙げられます。
- 保険会社から審査機関への書類提出が遅れている
- 提出書類に不備があった
- 医療照会に対する医師の対応が遅れている
また、異議申し立てをしてから結果が出るまで、申請から2~3ヶ月程度と言われています。場合によっては6ヶ月程度かかることもあるため、心しておきましょう。
交通事故の後遺障害認定審査のポイント
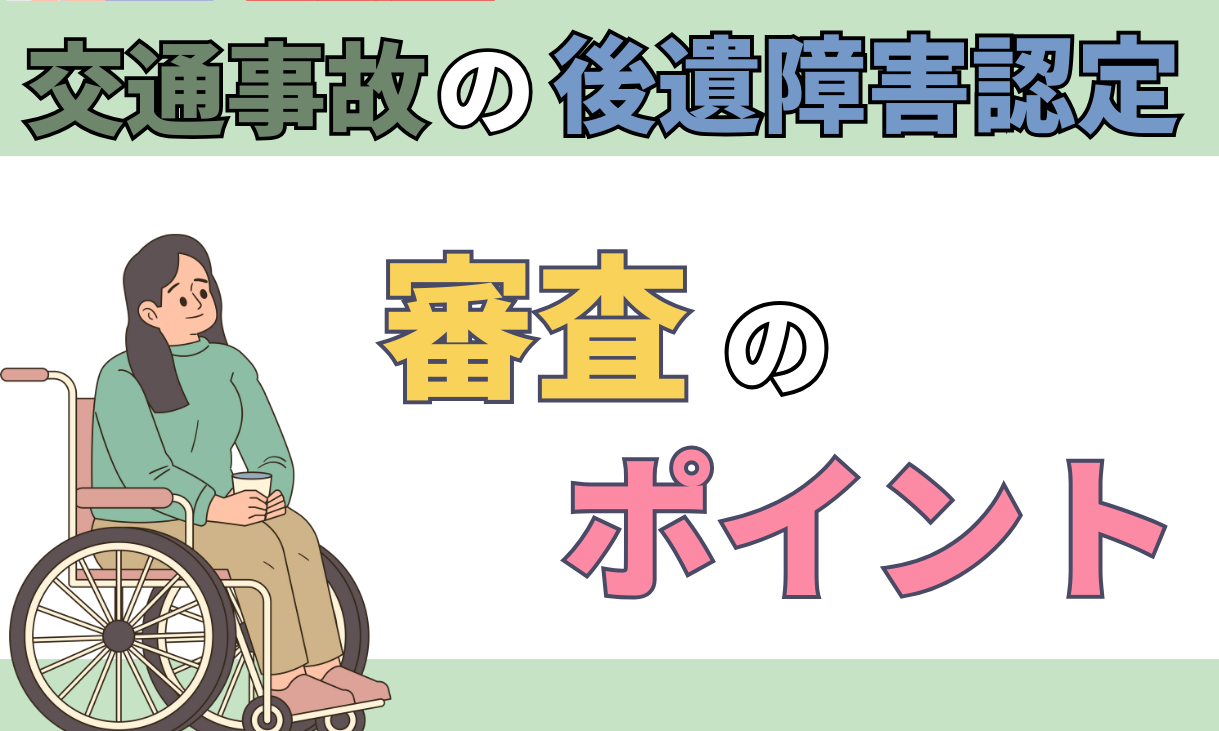
後遺障害認定を受けるために審査のポイントを抑えておくことが重要です。
以下の5つのポイントを解説していきます。
- 交通事故後にすぐ通院をする
- 後遺症が症状固定してからの審査が大切
- 医学的に証明できるよう病院で検査を受ける
- 交通事故と関連している後遺症であることを証明する
- 弁護士のアドバイスも受ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
交通事故後にすぐ通院をする
交通事故に遭った場合、すぐに通院を始めましょう。
後遺障害認定を受けるには、症状と事故の因果関係を証明する必要があります。
事故から通院開始まで時間が空いてしまうと、症状と事故の因果関係が認められなくなってしまうため注意しましょう。
また、後遺障害認定を受けるための通院期間は6ヶ月以上かつ適切な頻度で通院することも大切です。
「治療に対して消極的だったため、後遺症が残った」と判断されないために、適切な頻度で通院する必要があります。
しかし、必要以上に通院してしまうと過剰通院を疑われる可能性もあるため注意が必要です。
過剰通院と判断された場合は慰謝料を減額される場合もあります。
通院頻度は医師と相談し、決めるようにしましょう。
後遺症が症状固定してからの審査が大切
症状固定とは、これ以上治療を行っても症状が改善せず、後遺症が残った状態です。(症状固定とはコチラ)
症状固定と診断されていない場合、「治療を続けていれば怪我は治り、後遺症にならなかった可能性がある」と、認定を受けられない場合があります。
そのため、後遺障害認定を受ける場合は必ず症状固定と診断されてからにしましょう。
また保険会社によっては治療費の打ち切りにあわせて、通院をやめるように打診してくる場合もあります。
しかし保険会社の言う通りに通院をやめてしまうと、症状固定と判断できず後遺障害認定を受けられない可能性が高まります。
治療費の打ち切りを打診された場合は、医師に相談し、必要があれば延長の交渉を行いましょう。
医学的に証明できるよう病院で検査を受ける
後遺障害認定を受けるには、医学的な証明が必要です。
症状の有無や程度など医学的な検査を行い、客観的なデータを作成しましょう。
しかし、医師によっては後遺障害認定に必要な検査を提案してこない場合もあります。これは症状の治療に必要な検査と後遺障害認定に必要な検査が同じではないケースが多いからです。
この場合、被害者側から医師に検査をお願いする必要があります。後遺障害認定に必要な検査が分からない場合は、交通事故に強い弁護士に相談するといいでしょう。
交通事故と関連している後遺症であることを証明する
後遺障害認定を受けるには交通事故による後遺症であることを証明しなければなりません。
交通事故に遭ってから一貫した症状があることを伝える必要があります。
症状を伝える際は「事故直後から手足がしびれる」「事故に遭ってから肩の痛みが引かない」など具体的に伝えましょう。
反対に「事故直後は痛みが酷かったけれど今はそれほどでもない」「事故に遭ったときは肩が痛かったが、今は腰が痛い」など一貫性がない症状を伝えてしまうのはNGです。
医師がそのまま後遺障害診断書に記載してしまうと、交通事故による痛みではないのではないかと判断され、後遺障害認定が受けられない可能性があります。
症状を伝える場合は、症状が事故直後から一貫しており、交通事故による後遺症だと伝えることが重要です。
弁護士のアドバイスも受ける
弁護士のアドバイスを受けるのも、後遺障害認定のポイントの1つです。
特に医師が作成する後遺障害診断書は、後遺障害認定が受けられるかどうかだけでなく、等級の結果を大きく左右します。
しかし、よほど交通事故に詳しい医師や後遺障害認定に強い医師でない限り、認定を受けられるような内容を作成できないケースは多いです。
また、内容の修正を医師にお願いする場合にも、具体的に何を伝えればいいのか分からない人は多いでしょう。
その点、弁護士のアドバイスを受けることで後遺障害認定を受けられる可能性は高まります。
弁護士サポートが手厚い整骨院や交通事故治療を得意としている整骨院を、あなたの自宅近くから事故治療ナビがご案内します。条件に合った整骨院探しを無料でサポート。24時間電話・LINEで相談受付中です。また、今ならお見舞金20,000円をプレゼントしています。この機会にお気軽にお問い合わせください。





 事故治療ナビについて
事故治療ナビについて お客様相談窓口
お客様相談窓口 お見舞金について
お見舞金について 会社概要
会社概要