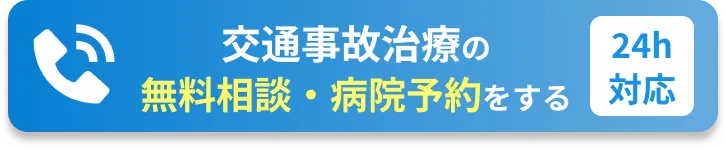交通事故の頸椎捻挫で後遺症は残る?後遺障害認定や慰謝料の受け取り方を解説

交通事故による頸椎捻挫で後遺症が残ってしまった、後遺障害認定や慰謝料に関して損しないように理解しておきたいという方に向けて、頸椎捻挫に関する情報を分かりやすくまとめました。
痛みが残っていても改善傾向がなければ、治療が終わったと判定され保険会社からの治療費を受け取れない可能性があります。
ただし条件に当てはまれば、後遺障害認定が受けられるかもしれません。後遺障害認定を受けるポイントについても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
頚椎捻挫の後遺症の種類・症状
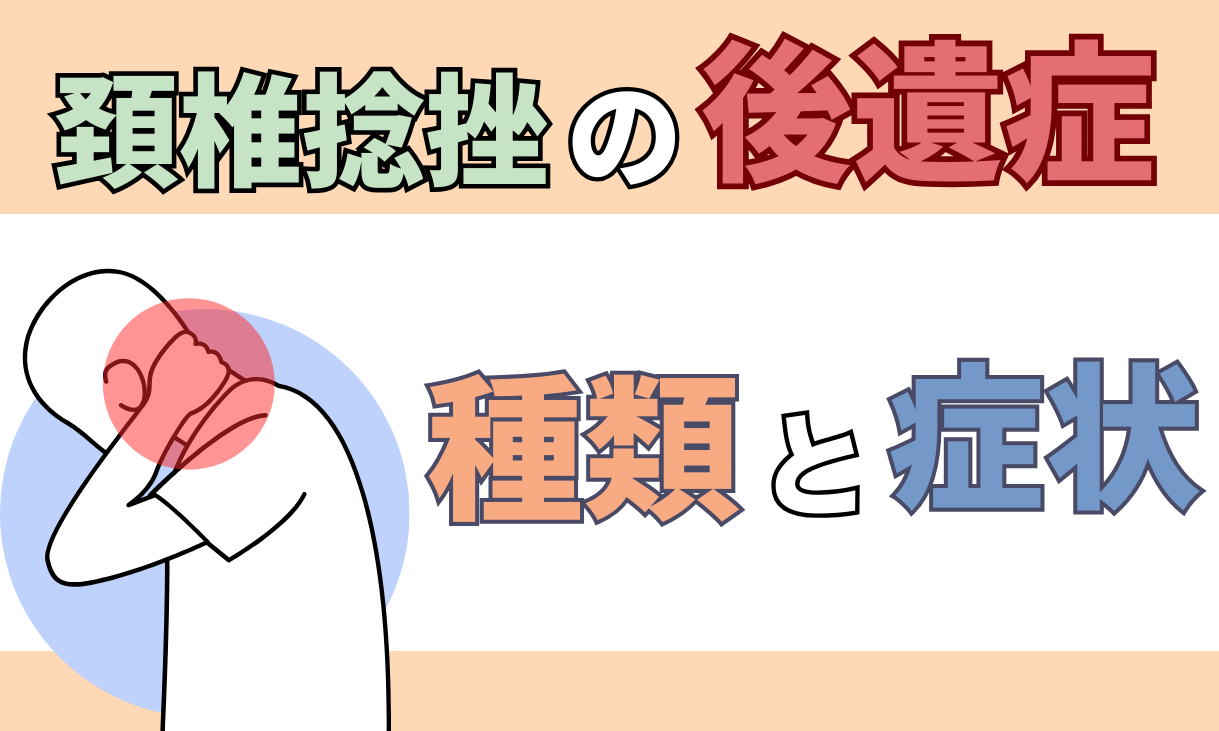
頚椎捻挫(むちうち症)の正式名称は外傷性頚部症候群で、主に首の動きや急激な刺激が影響し発症します。
頚椎捻挫の後遺症の症状
交通事故では、後ろもしくは側面から衝突されることで頭蓋骨が上下左右に揺さぶられ発症するのが典型例です。首がムチのようにしなることから、むちうちと呼ばれるようになりました。
まずはこの頚椎捻挫について、後遺症の種類と症状を詳しく紹介します。
| 症状 | 内容 |
| 動かしたときに首などの身体が痛む | 身体を動かしたときに特定の部位に痛みを感じます。交通事故により急激な力が加わったことで捻挫をしている状態です。主に首に痛みを感じるケースが多いです。 |
| 頭痛・首の痛み(頚部痛)・肩こり | 首や肩周りの筋肉が引っ張られたことで血流が悪くなり、頭痛や首の痛み、肩こりを発症します。捻挫の治療が快方に向かえば、それに伴って頭痛も回復していくケースが多いです。 |
| 倦怠感・耳鳴り・めまい・耳鳴り・動悸・吐気 | 交通事故により急激な力が加わることで筋肉が引っ張られたり打撲を負ったりすることで、筋肉が硬くなり倦怠感を覚えることもあります。衝撃で内耳神経、脳幹に損傷を負えば耳鳴り、めまい、動悸、吐気を発症することもあります。 |
| 痺れ | 交通事故により筋肉が引っ張られることで、硬くなったり関節の動きが悪くなったりします。筋肉の収縮により首回りの神経が圧迫されれば、痺れが生じます。神経根の損傷や圧迫も、痺れに繋がることが多いです。上肢に痺れを感じるケースが多いといえます。 |
これらの頸椎捻挫や後遺症にお悩みの方に、事故治療ナビがおすすめの整骨院を24時間無料でご案内します。今ならお見舞金20,000円贈呈中。交通事故治療対応・後遺症を残さない治療・リハビリが得意など、こだわりの条件に合った交通事故治療対応の整骨院探しをサポートします。
頸椎捻挫の後遺症でもらえる慰謝料の相場
具体的な慰謝料について、弁護士に依頼した場合に使用される基準では以下の表が目安となっています。
|
入院 \ 退院 |
0ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
| 1ヶ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2ヶ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3ヶ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4ヶ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5ヶ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6ヶ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7ヶ月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8ヶ月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9ヶ月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10ヶ月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
例えば、頸椎捻挫で3~6ヵ月ほど通院した場合、上記の表を参考にすると
1ヵ月の通院で19万円、3ヵ月程度の通院で53万円の慰謝料が算定されます。
頸椎捻挫で後遺障害認定を受ける流れ
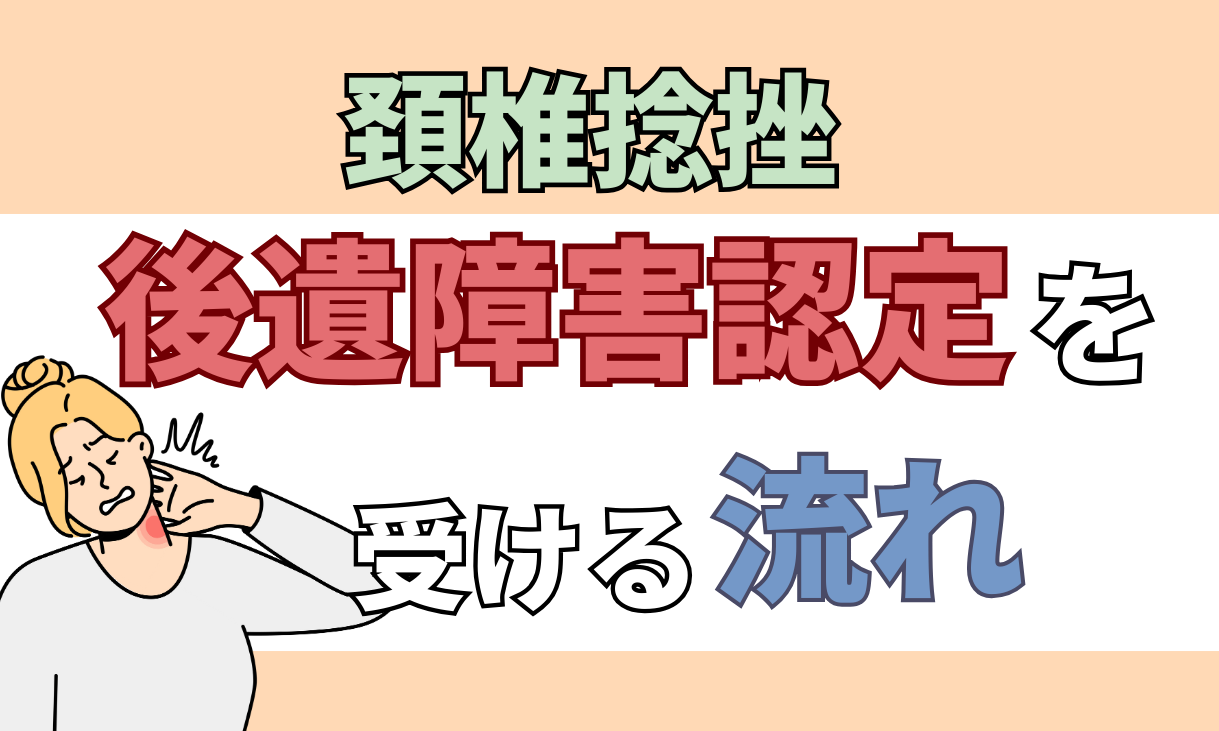
頸椎捻挫で後遺障害認定を受けるための流れを紹介します。必要な書類の他、申請方法をまとめました。頸椎捻挫の後遺症が疑われる場合は、参考にしてください。
病院に月1回以上通院する
後遺障害診断を医師に書いてもらうためには、定期的に医療機関への通院が必要です。
軽微な症状だとしても、必ずコンスタントに通院するようにしてください。通院頻度が低いと、認定が難しくなる場合があります。
症状固定の診断をうけ、診断書を書いてもらう
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復や改善が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定の判断が出されるとその時点で治療期間が終了し、治療期間にかかった治療費や入通院慰謝料、休業損害などが算定されます。
症状が一進一退で改善しない場合には、どこかで区切りをつけないと入通院慰謝料の金額は算定できません。
そこで、いったん治療期間を区切るために症状固定が設けられました。症状固定の判断は基本的に医師が行います。そして、症状固定時に残存している症状が「後遺症」と呼ばれます。
そのため、医師から「症状固定」の診断を受け診断書を書いてもらう必要があります。
その他に必要な書類は以下の通りです。
【事前認定に必要な書類】
- 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
【被害者請求に必要な書類】
- 支払請求書
- 診療報酬明細書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 印鑑証明書
- 休業損害を証明する書類
- レントゲン写真など
- 通院交通費明細書
- 付添看護自認書
自賠責保険に後遺症認定の申請をする
後遺障害の認定を受ける方法は、事前認定と被害者請求の2つです。
- 事前認定:加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定を申請する方法
- 被害者請求:被害者自身が損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定を申請する方法
事前認定は、加害者側の保険会社が申請手続を行ってくれるため被害者請求に比べて時間がかからないことがメリットです。一方で、加害者側の保険会社に申請手続を任せるため、必要最低限の書類で申請され、適切な認定を受けられない恐れがあります。
被害者請求はご自身で書類作成や資料を集めなければいけないため、膨大な手間と時間がかかります。しかし、書類に不備や不足があっても対応できたり、認定を受けるうえで有利となる資料の追加ができるため適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
頸椎捻挫で後遺障害認定を受けるポイント
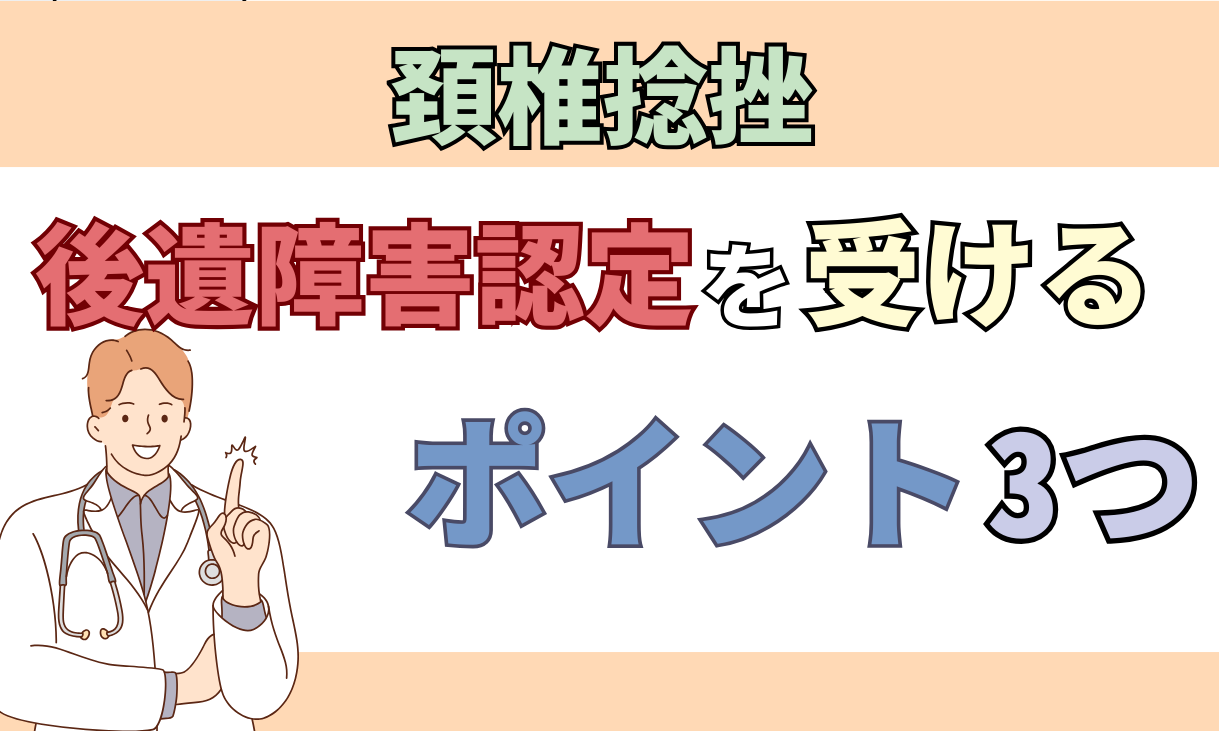
頸椎捻挫において後遺障害認定を受けるポイントは、以下の3つです。
交通事故との因果関係を証明
交通事故によって頸椎捻挫を発症したといった、事故とケガの因果関係の証明が必要不可欠です。ケガの原因が不明などといった文言があれば、後遺障害として認められないケースがあるため注意が必要となります。
因果関係を証明するものとしては、医師からの意見書も有効です。交通事故と頸椎捻挫の因果関係、ケガの程度などを記載してもらうと良いでしょう。
症状が継続していることを証明
症状固定の段階で、後遺障害として認められる症状が持続しているかは大切です。
症状固定とは、適切な治療を行っても症状が改善される見込みがない状態のことをさします。症状固定となった状態で後遺障害の症状が認められれば、後遺障害の認定率が上がるかもしれません。
医師からの診断書が重要となります。
神経の損傷や機能障害を証明
神経の損傷、機能障害などの検査の証明も重要なポイントです。MRI、筋電図、神経伝導検査などの検査結果を被害者請求で資料として添付することで、後遺障害認定率が上がるかもしれません。
添付できる資料は他にないか、よく検討することが重要といえます。
頚椎捻挫の後遺障害で認定される後遺障害等級
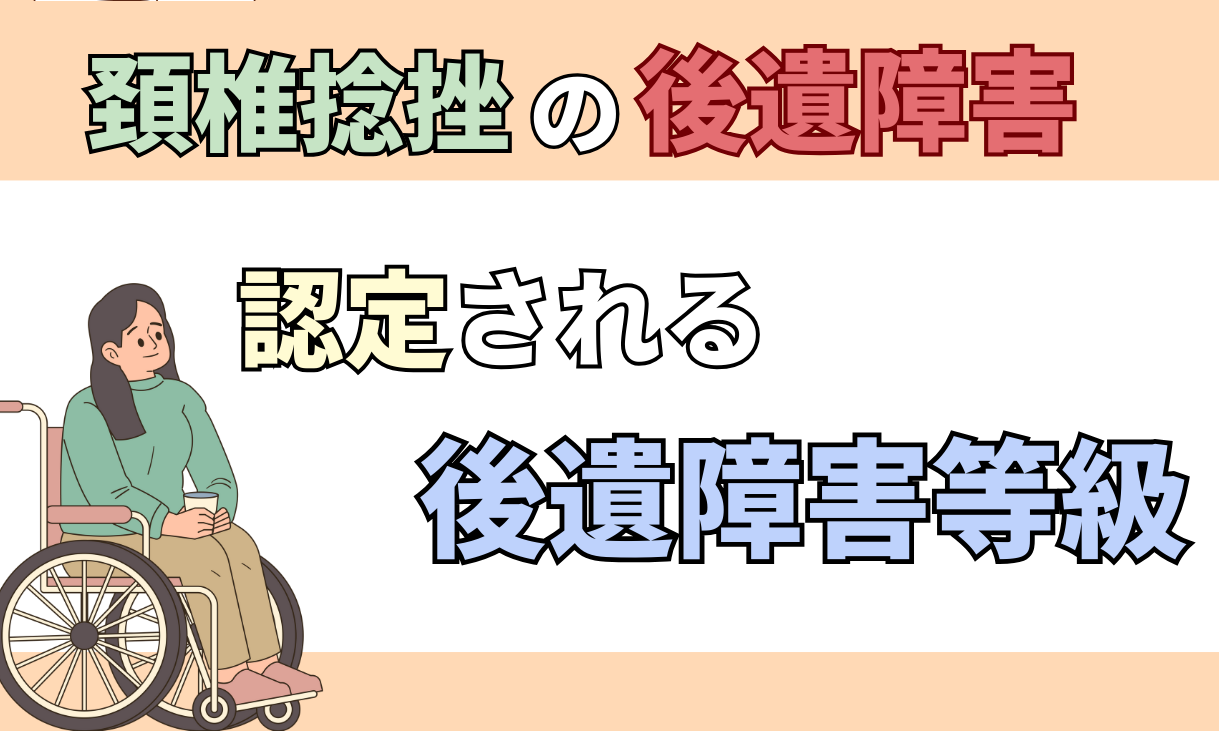
後遺障害は中枢神経系が1~9級であり、末梢神経系が12級もしくは14級となっています。頸椎捻挫の後遺障害は多くが末梢神経系のため、基本的には後遺障害14級もしくは12級になるといえるでしょう。
それぞれの特徴を紹介します。
後遺障害14級
局部に神経症状を残すものは、後遺障害等級14級9号に分類されます。
12級13号の後遺障害は客観的な初見が必要ですが、14級9号は自覚症状があれば認められることもあります。頚椎捻挫における局部とは、首のことです。首の痛み、上肢の麻痺や痛み、頭痛、嘔気なども14級9号の後遺障害等級に認定されることがあります。
なお将来においても改善しないと医師が認めていることが前提です。また症状が消滅する時間(雨が降ったときのみ痛みがあるなど)がある場合も、認定はされません。
交通事故によってケガをした因果関係の説明が必要となるため、車体の損傷が少ない小さな事故では認定されないケースも多いです。
後遺障害12級
局部に頑固な神経症状を残す場合は、12級13号に認定されることがあります。
14級9号との大きな違いは、自覚症状のみでは認定されないところです。他覚的な異常所見が必要であり、自覚症状のみで認められることはまずありません。
この場合の局部も、首をさします。症状としては、首の痛み、肩こりなどの症状の他、骨折、脱臼、椎間板ヘルニア、椎間板高の減少、筋力低下、筋肉の萎縮などがあげられます。
神経、椎間の異常に関してはレントゲンでの撮影ができないため、MRIでの診断が必要不可欠です。筋電図、神経伝導検査などの検査結果も客観的な所見として認められます。
頚椎捻挫の後遺症の治し方
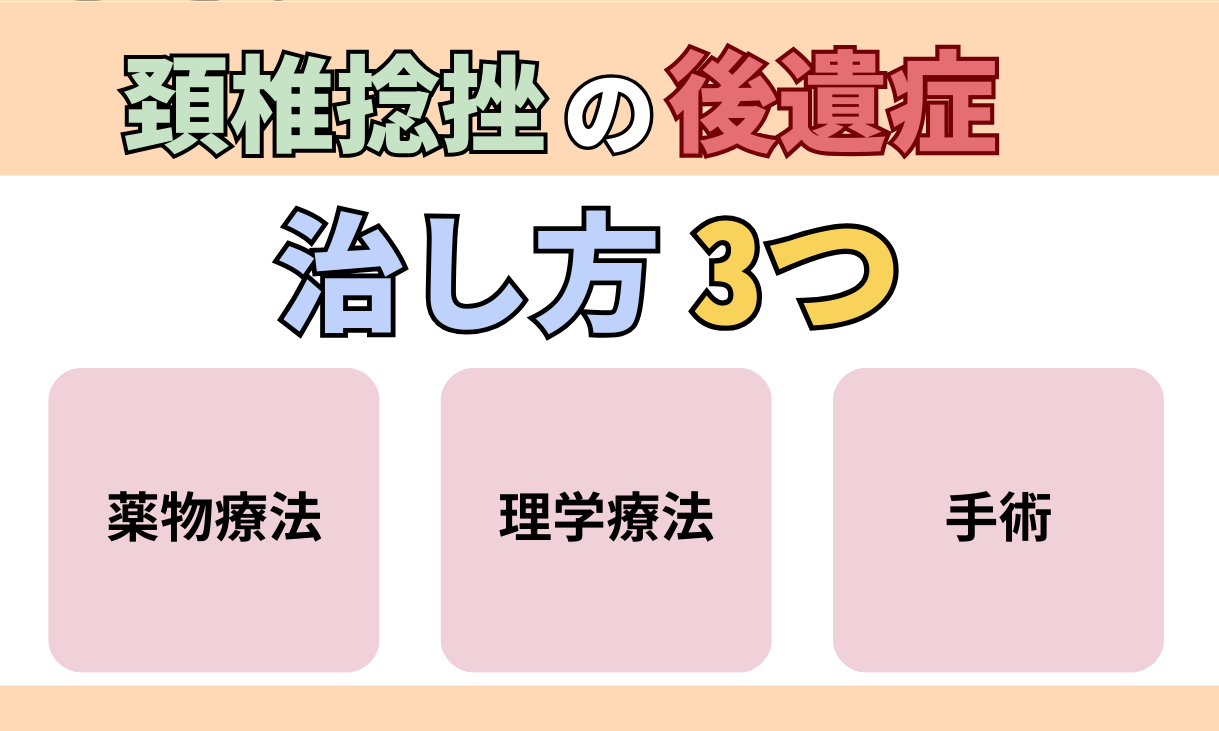
捻挫とは、不自然な方向へひねったり力が加わったりすることで関節の靱帯、腱、軟骨が傷つくケガのことです。捻挫は症状の重さによりⅠ度~Ⅲ度に分けられ、それぞれ治療方法が異なります。重症度について、以下の表にまとめました。
| 損傷レベル | 治療期間 / 安静期間 | 損傷の程度 | 症状・状態 | 推奨される治療内容 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ度 | 治療期間:半月~1ヶ月 安静期間:3日~2週間 |
靭帯の一部分が損傷している | 軽度の痛み・腫れ。関節の不安定感は少ない。 | RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上) サポーター・テーピング 手技療法・矯正施術 |
| Ⅱ度 | 治療期間:1~4ヶ月 安静期間:3週間程度 |
靭帯の部分断裂が発生している可能性あり | 中程度の痛み・腫れ。関節の可動域制限あり。 | RICE処置に加え、症状により医師の診察や画像診断が必要 固定・リハビリなど段階的な治療 |
| Ⅲ度 | 治療期間:半年以上 安静期間:症状の程度による |
靭帯が完全に断裂している可能性あり | 強い痛み・腫れ。関節が不安定で歩行困難。 | 強固な固定または靭帯の縫合手術が必要 長期リハビリ |
完治せず後遺症となった場合は、次に紹介する「薬物療法」「理学療法」「手術」などの治療となります。頚椎捻挫による後遺症の治療方法、期間などについて見ていきましょう。
薬物療法
頸椎捻挫の後遺症に対する一般的な治療方法は、安静にしつつ痛み止めなどを服用する薬物療法です。
首の痛みが強く正しい姿勢をキープできない場合には、首を保護するための頚椎装具を装着することもあります。消炎鎮痛剤を服用することで、首の痛みが軽減され血流が改善される効果が期待できます。
理学療法
理学療法とは身体を動かしやすくすることを目的としており、低周波、温熱、マッサージなどの物理的な手段を通じて行う治療方法です。
頸椎捻挫で行われる治療方法は、温熱、低周波、牽引、セラピストによるマッサージなどがあげられます。痛みを和らげると同時に、身体が動かしやすくなるといった効果が期待できます。
手術
頸椎捻挫は保存療法が主流の治療方法であり、基本的には手術は行いません。しかし上記の治療方法で痛みが和らがない場合には、手術治療が提案されるケースがあります。
クリニックにより対応が異なりますが、手術治療をする前にAKA-博田法などの治療が開始されるケースもあります。なお手術をすれば必ず痛みが緩和・治るわけではなく、人によっては痛みが変わらないケースもあるためよく検討することが重要です。
頚椎捻挫の後遺症チェックリスト
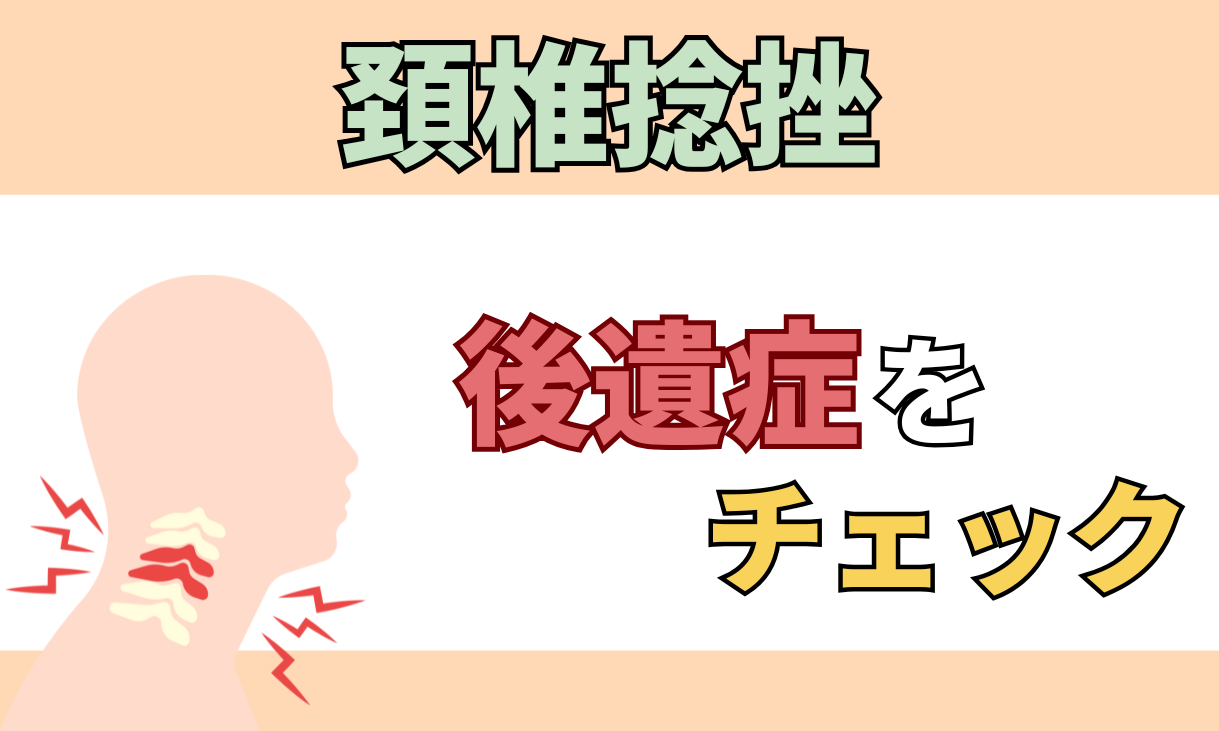
頸椎捻挫における後遺症のほとんどは、末梢神経における障害です。主な後遺症の症状を以下にまとめましたが、以下に記載された症状以外で気になる点があれば迷わず医師に相談することがおすすめです。
自覚できる症状としては以下のようなものがあげられます。
- 運動麻痺(手足、もしくは身体全体が思うように動かせない)
- 中枢性麻痺(運動障害、感覚障害、不随意運動など)
- 末梢性麻痺(顔面麻痺など)
- 知覚障害(光、音、温度など外部の刺激が上手く感じられない)
- 知覚過敏(光、音、温度などを過敏に感じる)
- 知覚鈍麻(光、音、温度などの刺激に鈍くなる)
- 異常知覚(刺激がないのに痛み、痺れを自覚する)
- 自律神経系障害(起立性低血圧、めまい、瞳孔異常)
- 自律神経失調症(顔が火照る、手足が冷たい、動悸など)
頸椎捻挫においては、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経系の障害が見られます。上記の症状の他に気になる症状があれば、医師に相談することがおすすめです。





 事故治療ナビについて
事故治療ナビについて お客様相談窓口
お客様相談窓口 お見舞金について
お見舞金について 会社概要
会社概要