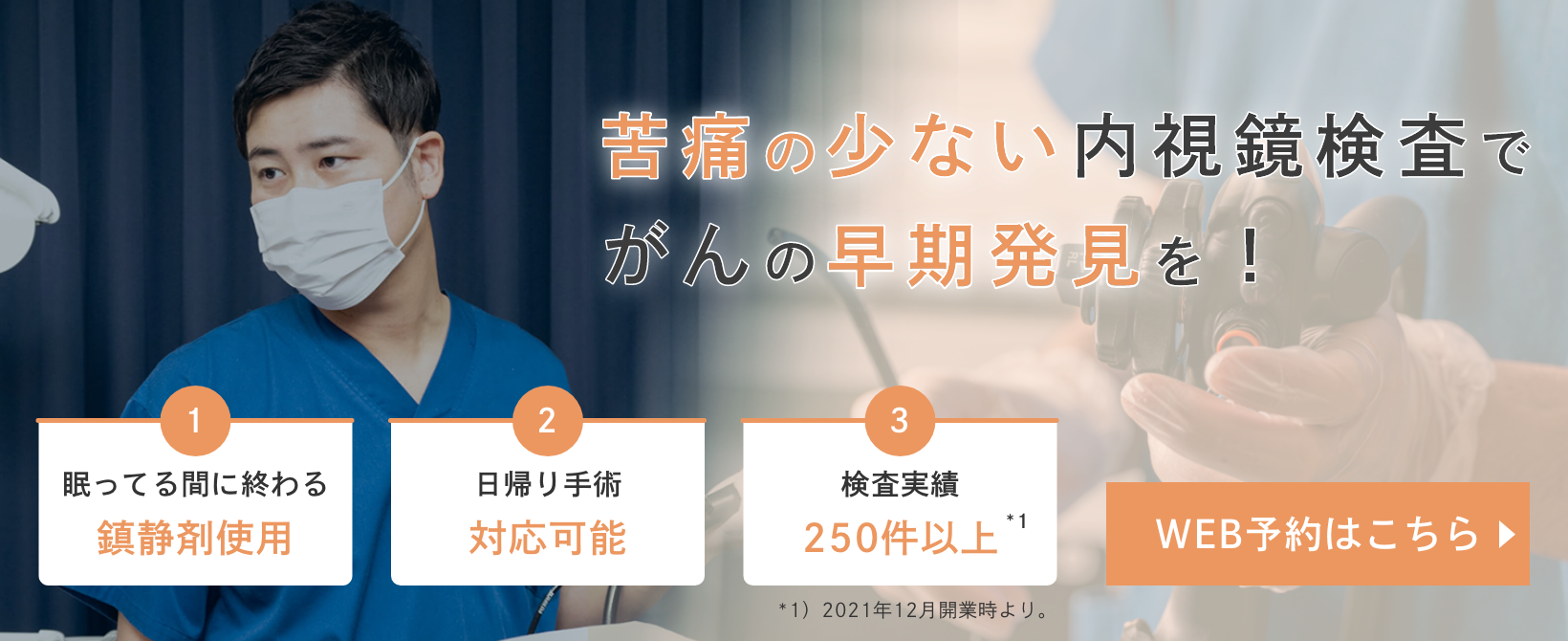胃の精密検査を受けるとき、多くの場合で内視鏡が用いられます。
これまでの内視鏡は、口から挿入することが一般的でした。しかし、現在は技術の進歩に伴い細径化が進み、鼻から挿入できる内視鏡が普及しています。
鼻から挿入する内視鏡は吐き気を催しにくいことから、楽だと感じる方は多くいます。しかし、必ずしも全員がそう感じるとは限りません。
この記事では、鼻と口から挿入する内視鏡のそれぞれのメリットとデメリットを紹介します。
これから内視鏡検査を受ける予定がある方や、鼻と口どちらにするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
内視鏡の基本

内視鏡には、用途別にさまざまな種類があります。
そのなかでも最も使用頻度が高いのは、胃や大腸などの消化器官を検査するための内視鏡です。内視鏡検査を受けたことがなくても、知っている、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
内視鏡の主な使用目的は、食道や胃、大腸にある病変の発見と観察です。肉眼だけの確認に留まらず、写真や動画を活用してより精度の高い検査が可能です。
また、内視鏡は観察だけでなく組織の採取もできます。採取した組織は顕微鏡や検査機器で詳細に分析することができ、病変の状態を正確に把握することが可能です。
そのため、胃や大腸などの消化器官の粘膜組織を観察するために有効な手段の一つと考えられています。
さらに、現在の内視鏡は治療や処置も可能です。
ポリープなどの病変はもちろん、早期の胃がんや大腸がんの切除もでき、腹部にメスを入れて手術するより負担が格段に少ないという特徴があります。
一部のがんは、早期発見・治療により完治を目指せます。そのため、定期的な内視鏡検査は非常に重要です。
経口内視鏡

口から挿入する内視鏡を、経口内視鏡と呼びます。
昔からあるタイプの内視鏡であり、嘔吐反射が起こりやすいことや痛みがあることから、多くの方のトラウマの元凶といわれることがあります。
昔の経口内視鏡は太く、挿入時は不快感が強いものでした。しかし、現在は技術の進歩により以前より細くなり、カメラの精度も高くなっています。
また、内視鏡検査が患者さんの負担にならないように、ほとんどの医療機関で静脈麻酔や鎮痛剤が使用されています。
以前のような痛みや苦しさはほとんどなく、寝ているような状態で検査を受けることが可能です。
ここでは、経口内視鏡のメリットとデメリットを紹介します。特徴を把握してご自分に合った検査方法か見極めることが大切です。
メリット
経口内視鏡はスコープの径が太い分、さまざまな機能を備えることができます。
付属されたライトはとても明るく、より鮮明に内部の観察ができます。また、搭載されたカメラは高解像度・高機能なものであるため、病変を発見しやすい特徴があります。
高い水準の機能が備わっていることから、比較的短時間で検査ができるメリットがあり、リスクが高いと判断されるケースで特に効果を発揮します。
現在、多くの医療機関では静脈麻酔を打ってから内視鏡検査を行います。
以前の内視鏡検査のような痛みや苦痛はなく、眠っているような状態で楽に検査を受けることができます。
デメリット
経口内視鏡で検査をする際は、静脈麻酔(鎮静剤)を使用します。眠ったような状態になるため、検査中の記憶がほとんどありません。
帰宅する際は自動車や自転車を使用することができず、行動を制限されてしまいます。
検査後は病院内で安静にする必要があり、鎮静剤の効き具合によっては、通常約1時間の滞在時間がそれより長くなる可能性があります。
急いでいる方にとっては、これは大きなデメリットといえるでしょう。
経鼻内視鏡

鼻から挿入する内視鏡を経鼻内視鏡と呼びます。
経口内視鏡に比べてかなり細くなっており、鼻からの挿入が容易であることが特徴です。
触れると嘔吐反射を起こす舌の根元に触れないことから、比較的楽な検査方法として認識されています。
このようにメリットを多く感じる経鼻内視鏡ですが、必ずしも全員に向いているとは限りません。
場合によっては経口内視鏡の方がよい場合もあるため、まずは特徴を把握して自分に合った検査方法かどうかを見極めることが大切です。
ここでは、経鼻内視鏡のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
経鼻内視鏡の一番のメリットは、嘔吐反射が少ないことです。
経口内視鏡のように舌の根元に触れることがないため、内視検査でよくある「オエッ」となることが少ない傾向にあります。
鎮静剤を使用する必要はなく、ゼリー状の局所麻酔のみで検査中の不快感は解消できます。
そのため、検査後すぐに車の運転や仕事をすることが可能であり、忙しい方でも無理なく検査を受けることが可能です。
また、経鼻内視鏡は口が塞がっていないため、検査中に医師と会話できます。気になることや違和感がある場合は、すぐに医師とコミュニケーションがとれるため安心です。
内視鏡検査が初めてで不安な方や、以前経口内視鏡で検査を受けた際に苦しい思いをした方には、経口内視鏡をおすすめします。
デメリット
メリットが多い経鼻内視鏡ですが、当然デメリットもあります。
よく問題となるのが、患者さんの鼻腔が極端に狭い場合です。経鼻内視鏡は直径5〜6mm程度ですが、鼻腔がこれより狭い場合は物理的に挿入できません。
このような場合は、通常の経口内視鏡で検査することになります。
経鼻内視鏡で検査を受けたくても受けられないケースがあるのは、大きなデメリットといえるでしょう。
また、鼻から通す性質上、鼻に水が入ったときのようなツンとする痛みや頭痛を感じる場合があります。
こういった症状を緩和するために局所麻酔をしますが、麻酔の影響で検査後に鼻水やくしゃみが出ることがあります。
内視鏡自体が細いため、経口内視鏡に比べ検査に必要な時間が少しだけ長くなることは覚えておきましょう。
内視鏡で発見できる病気

内視鏡検査は、自分自身では気づけない病気を発見するのに効果的です。
食道や胃、大腸などの病気は初期症状や自覚症状がない場合が多く、気づいたときには手遅れになっていたというケースも珍しくありません。
定期的に内視鏡検査を受け、病気を早期発見・治療することが大切です。ここでは、内視鏡で発見できる代表的な病気を紹介します。
胃がん
胃がんは、胃の内側にある粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞に変化し、増殖を繰り返すことで発症する病気です。
がんが大きくなるにつれ、徐々に外側へ進行します。外側に到達した場合は、大腸や膵臓など、ほかの臓器に転移する可能性があり大変危険です。
また、がん細胞がリンパ液や血液の流れに乗って移動するケースがあり、胃から離れた臓器で転移が起こり増殖していく恐れがあります。
胃がんは初期症状がないことで知られており、進行しても気づかない方がほとんどです。
代表的な症状として、胃痛や胸やけ、食欲不振などがあります。しかし、これらの症状は身体のちょっとした不調でも起こる可能性があるため、たとえ胃がんであっても気づかない方が多いです。
胃がんは早期発見・治療することで、完治が目指せる病気です。
少しでも違和感を覚えた場合は定期健診を待たずに、すぐ医療機関で受診するようにしましょう。
食道がん
食道がんは、食道内のあらゆる場所で発症する可能性がある病気です。
日本人でも発症する方は多く、約半数が食道の中央付近で発生しています。
食道がんは食道の内側の壁を覆っている粘膜の表面に発生し、同時に複数箇所で発生することも珍しくありません。
胃がん同様、食道がんは徐々に外側へ向かって進行します。外側へ到達した際は、大動脈や気管などの周囲の臓器に直接広がる可能性が高まります。
また、食道内にある血管やリンパ管にがん細胞が侵入する場合もあり、血液やリンパ液の流れに乗って体中に転移するため注意が必要です。
初期症状はほとんどなく、進行することで飲食時の違和感や体重の減少といった症状が現れます。
大腸がん
大腸がんはその名の通り、大腸に発生するがんです。
正常な粘膜から直接がんになるケースもありますが、良性ポリープががん化して発生することがあります。
日本人の場合は、直腸やS状結腸に発生しやすいと考えられています。
他のがん同様、大腸がんは初期症状がほとんどない病気です。そのため、気づかないうちに進行し、定期検査で発見されることも珍しくありません。
主な症状として血便や下血があり、がんが進行すると慢性的な貧血になることがあります。
痔を患っている場合にも見られる症状であり、すぐにはがんと気づかない方がほとんどです。
大腸がんに限らず、がんは早期発見・治療することで完治できる場合があります。少しでも不快感や違和感を覚えた場合は、早めに医療機関で受診することをおすすめします。
まとめ
この記事では、経口内視鏡および経鼻内視鏡のメリットとデメリットについて解説しました。
従来の内視鏡検査を受けたことがある方は、痛い・苦しいというイメージを持っている方が多いです。
また、そういったイメージが広がり内視鏡検査をまだ受けたことがない方でもマイナスのイメージを持つ方が増えていることも事実です。
しかし、内視鏡は年々進化しており、検査を行う医療機関も患者さんが可能な限り苦しい思いをしないようにさまざまな工夫をしています。
以前のような苦痛を体験することは少なくなり、気軽に受けられる検査に変化しています。
どの検査方法が向いているかは人それぞれですが、経口内視鏡と経鼻内視鏡どちらを選んでも結果に相違はありません。
それぞれの特徴を把握して、自分が受けたいと思う検査方法を選んでください。
都営新宿線「曙橋駅」A2出口、都営大江戸線「若松河田駅」若松口のどちらからも徒歩6分の「おうえケアとわクリニック」では、痛くない、苦しくない内視鏡検査に取り組んでいます。
鎮静剤を使用するため、経口内視鏡と経鼻内視鏡、どちらを選んでも楽に検査を受けることができます。
また、日々忙しくて時間が取れない方のために、胃と大腸の内視鏡検査を同日に受けられるようにしています。事前にお問い合わせいただければ、無理のないスケジュールで検査を行います。
内視鏡検査で苦しい思いをしたことがある方やこれから受けたいと考えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。